今回は,国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)が出版している「公式TOEIC Speaking & Writingガイドブック(旧TOEICスピーキングテスト/ライティングテスト公式ガイド)」についてレビューしてみようと思います。
S&Wテストの全体像を把握できる公式ガイドブックということで,公開テストを受験される方は是非とも手に入れてやっておきたいものです。
もっとも,公式からはもう1冊,公式TOEIC Speaking &Writingワークブック(旧テストの解説と練習問題)という書籍が出ていますが,そちらは実践的な形式で問題をたくさん解きたい方に向いています。
逆に,本書では採点基準をより詳しく理解することができるため,実際に試験を受けた人の解答例を自らの視点でもって分析をし,そこで得た知見を自分独自の学習戦略に役立てるといった使い方が可能です。
どちらか1冊を選ぶというのであれば,私はワークブックの方をおすすめしますが,両者の特徴を予め知っておくことは重要でしょう。
公式TOEIC Speaking & Writingガイドブックの概要
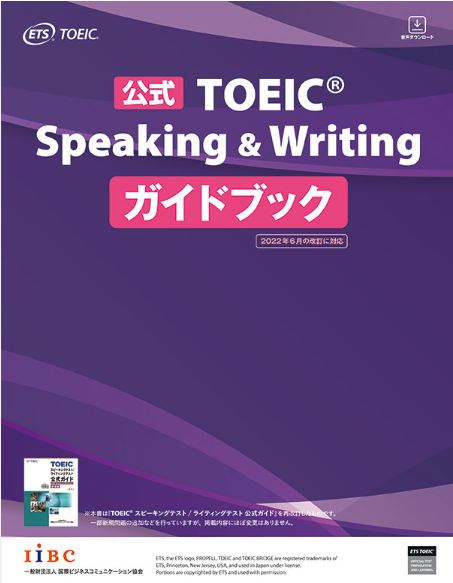
スピーキングとライティング能力は,リスニングやリーディング能力と相関がみられることは確かですが,後半の2つとは異なる能動的な行為となることから,習得するために別で努力することは必要で,TOEIC S&Wテストは,職場や日常生活で英語を利用している方の実力を測るために開発されました。
その証拠に,本番のテストにおいては,声を出したり記述式の問題を解くなどして,ビジネスシーンで実際に話すであろう内容の英語を用い,コミュニケーションスキルの高さを示す必要があります。
TOEICテストの種類については,それ用に語った以下の記事で詳しく触れましたが,S&WはiBT(internet-based test)というシステムを採用しており,PCとヘッドセットを使って解答するところが大きな特徴です↓
ところで,公式TOEIC Speaking & Writingガイドブックが初めて出版されたのは2006年の11月のことですが,その内容を一部改訂し,2010年の11月,そして2022年の12月に新装版が刊行されました。
もっとも,これらの間で掲載されているサンプル問題や練習テストの内容にほとんど変更はなく,それは公式サイトの方でもアナウンスされており,現行のテストにおいても旧式のもので対応可能です。
実際,私も2022年11月のテストの対策に2010年版のものを利用しました。
ただし,スピーキング範囲において,描写問題の変更(制限時間と問題数が変わった)と,解決策を提案する問題が無くなったなどの違いはあるので,不安な方は他社から出ている最新の対策本を買っておくのが無難でしょう。

さて,ここからは本ガイドブックの特徴について述べていきますが,スタジオで録音した音源ではなく,実際の受験者による生々しい解答例がたっぷり収録されているところがまず挙げられます。
全体のページ数も約300ページと多めで,A4変型判というサイズ感は自宅学習に向いていて,定価は3080円と手ごろです。
音声を公式TOEICアプリの方からダウンロードできるところも,人によっては使いやすいと感じるのではないかと思います。
次章から内容について詳しく述べていきますが,TOEICの製作元であるETSが本書の問題を制作しているため,難易度は実際のテストと変わりません。
使い方は,まず最初に解答例を通して採点方式について理解し,その後,2回分の練習テストで本番形式に慣れるといった流れになります。
さて,本書が対応しているレベルですが,TOEIC L&Rで500点以上取れる方であれば誰でもおすすめです。
構成は,試験の特徴についての簡単な説明があった後,大きく分けて3つの章からなります(以下は2010年版で,ページ数などが現行のものとやや異なることに注意してください)↓

第1章ではスピーキングテストの問題を内容別に詳しくレビューし,続く第2章でライティングの問題を題材にして理解を深めていきましょう!
そして最後の第3章において,いよいよスピーキングとライティング両者の練習テストを解くことで,総仕上げとなります。
第1章スピーキングテストサンプル問題の詳細

第1章で扱うのはTOEICのスピーキング問題です。
全11問からなりますが,問題タイプとしては大きく5つに分けられます(以前は,解決策を提案する問題があったので計6つでした)。
そしてその1つ1つに対し,以下の順番で解説が加えられていく流れです↓
- 問題の概要
- アドバイス
- 問題形式
- 採点ポイント
- 問題例(AとBの2問)
- 採点スケール別の解答例と講評
ここでは5つの問題タイプのうち,写真描写問題を例に,上の手順を確認してみましょう!
まず問題の概要ですが,設問数や解答時間に加え,課題内容・解答のポイント,そして高スコアを取る秘訣が箇条書きにされています(画像左)↓

右ページにはアドバイスが載っていて,本番における注意点と家で対策するときの勉強法についての記述を確認することができました。
ページをめくって,今度は問題形式と採点のポイントについてみてみましょう↓

スピーキングの章では実際の音声を確認することができますが,本番でPC画面に表示される文面や対訳が載っているところが親切です。
もっとも,公式HPでサンプル問題を解いたことがある方であればわかるように,上の問題はお馴染みの問題の使いまわしで,この問題に関して解答例などは提示されません。
右ページにある採点ポイントでは,どういう基準に則って採点が行われるのかを再確認することができます。
意外と見過ごしがちな内容ですが,本書においてはこの基準に注目することが大切になってくるわけで,そのころが本書の大きな魅力となっているわけです。
もちろん,上に書かれている基準だけではやや抽象的過ぎて十分とは言えません(公式HPにも同じものが載っています)。
そこで,この後3ページにわたって続く問題例とスケール別の解答例がようやく出番となるわけです。
全部で8人の受験者の解答と点数をスケール別に聞き比べながら,「こういう話し方ができると満点がもらえるのか」と参考にできたり,あるいは「こんなしゃべり方でも2点はもらえるんだ」といった安心感を得たりできます。
ちなみに,これらの音源は実際の受験者によるもので,本番を受けてみると「自分の解答例を書籍作成などに利用してもよいですか」などと問われることになるでしょう。
聴いた感想ですが,音質が粗い分リアルに感じられるはずです(現在,日本のテストセンターの録音環境は本書のものよりも圧倒的に良いです)し,途中で制限時間が来て,ブチっと終わってしまっている人も多数いました。
確かにネイティブ発音ではないですし,完璧な答案なのかすらわからないのですが,実際の受験者の人となりも垣間見え,英語学習の意欲が高まることは間違いなしです↓

日本人の解答と外国人の解答との間に,明らかな違いを感じ取ることができます。
なお,解答・講評例の合間には「まとめ」といった形で,心得めいたものが要約されていました。
これはスケール別に用意されていて,得点の低い解答からも何かしらの学びを得ることができます。
一個人の単なる感想ではなく,公式が書いたという点が重要で,以下のように明確な目標を提示してもらえることで対策が立てやすくなるでしょう↓

第2章ライティングテストサンプル問題の詳細

第2章ではライティングテストの問題を題材に学ぶことになります。
アドバイスと問題形式の順番が入れ替わっているものの,学ぶ手順は基本的に1章で紹介したものとほぼ共通です。
ライティングテストの問題タイプは全部で3つ(設問数は8問)と,スピーキング問題よりも少なくなってはいますが,その分,問題例の紹介が多くなっていてバランスが取れています。
ここでも,最初の写真描写問題を例に紹介してみますが,問題の概要と形式についてはこのような感じです↓

「非常に長い文や複雑な文を書いても加点されない・スペルミスなどは評価に影響しない」といった但し書きはとても役立つ情報です。
市販の参考書を読んでいた方からすると,誤解していたことが結構多いことに気づかされるように思われます(市販のものは難しく書きすぎているように感じます)。
本書が最初の1冊目である方は,
この本を通して実際の問題形式について知っておかなかったら,本番では一体どうなってしまっていたのだろう…
と,恐ろしく感じられるでしょう。
かなりの労力を費やすことになるS&Wテストですが,対策次第では実力が発揮されることなく終わりになってしまうことも十分考えられます。
その点,本書のアドバイスは具体的で実践的なものなので,どうすれば良い評価になるかだったり,どういった対策をすればハイスコアに繋がりやすいかなどについて理解しやすいでしょう。
もちろん,採点されるポイントもしっかりとまとめられています↓

問題例はこちらはA(1問目)となっていますが,これがFまであるので,本番よりも1問多い全6問です。
また,Aだけでも実際の解答例が採点スケール3が8人分,スケール2が3人分,スケール1の例が2つあるので,良い答案と悪い答案の両方から多くの秘訣を得ることができました↓

こちらは英文で書かれているので,スピーキングの章よりも確認がしやすかったです。
なお,第2章においては,音声で確認するところは特に見当たりませんでした。

第3章練習テストの詳細

第3章は音声素材を用いながら,実際のS&Wの模試を解くことになります。
音声をダウンロードする方式ではなく,CDだった時の収録時間を以下に示しますが,準備時間(無音の時間帯)も収録されていて,こちら側でそういった時間の工夫は必要はありません↓

ただし,音読問題などでは自分の解答を録音する作業が別途必要なので,スマホなどを使って録音するようにしてください。
また,旧版を使う方は本番と時間配分などが異なるので,各自調整して行いましょう。
ノンストップで練習テストが流れるので集中して問題を解くことができますし,その後の解答例の音源であったり,解答解説ページで和訳チェックのページだったりを使って,じっくり解説を読みこむこともできます↓

ETSが選んだ模範解答例なので,できるだけ多くを吸収してはさらに上を目指しましょう!

まとめ
以上,公式TOEIC Speaking & Writingガイドブックのレビューでした。
解答の完璧性にはやや不安が残るものの,本書を通してさまざまな勉強法について知ることで,TOEICに限らず,英語を上手く話したり書けたりするための正しい方法を学ぶことができます。
完璧でない答えの方が普通だとわかったり,外国人の方が頑張って答えている解答例を聴いたりすることで,不思議と自信を持って本番に臨めるようになることも本書を使うメリットです。
スピーキングの章を終えたときの感想ですが,アナウンサーの話す英語を意識的に多く聴くようになった他,英字新聞から短い英文を選び出して何度も音読するだとか,自分の英語を録音し,ネイティブが話す英語とどこが異なるのかをチェックする習慣が身に付きました。
ライティングは形式について学べたところが大きかったですし,本番でもそれに沿って書くことができて役に立ったように感じます。
是非とも,S&Wテストの準備段階において本書を使って学習しては本番に臨むようにしてください!
なお,本書で学ぶ前後に,冒頭のところで紹介した公式のワークブックを学んでおくと,相乗効果でより理解が深まるのでおすすめです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
