今回は,安倍晋三氏が近畿大学で行ったスピーチを基に,TOEICに役立つ知識を深めていきたいと思います。
なお,実際のスピーチは日本語で行われましたが,以下で紹介しているように英語に翻訳された動画も視聴可能です。
当記事では後者の原稿をメインとして扱い,スピーチを内容的にいくつかの段落に分けながら,まとまりごとに解説を加えていきたいと思います。
目次
安倍晋三氏の近畿大学卒業式スピーチについて
この安倍晋三氏のスピーチ動画ですが,2022年3月19日の「令和3年度近畿大学卒業式」においてゲストスピーカーとして招かれた時のものです。
全部で約15分間にわたるスピーチとなっていて,東日本大震災や安倍政権での自身の教訓をもとに,コロナ禍を経験した卒業生たちに対して今後の糧となる非常に重要なメッセージを贈っています。
大変ありがたいことにその内容はYouTubeの動画でいつでもだれでも視聴することができ,完全に日本語のオリジナル版以外に英語の字幕が付いた海外向けのEnglish versionまでもが存在し,上に示した動画がまさにそれです。
オリジナル版がすでに500万再生を超えていることからも明らかなように,その内容は何度も観返すに値するものであり,これからも多くの人々の心の支えとなるでしょう。
そしてそのスピーチを英語に翻訳したものはTOEICを勉強する上でも十分役立つものとなっており,以下の記事で述べたように,優れたスピーチを題材として学びたい方にとってみればうってつけです↓
スピーチを丸ごと暗唱することでそのまま使える表現が数多く手に入りますし,後に登場するAIが生成した音声を使えば,音読の題材としてや同時通訳の練習にも役立てられるでしょう。
翻訳されている内容は日常的なものから政治的な内容までを幅広くカバーし,温かいユーモアを交えつつ前向きになるメッセージにあふれているため,練習していて辛いと感じるところはありません。
逆に,変に視聴者に気を使わずに済む分(聞き手に英語ネイティブを想定しているため),出てくる語彙レベルは高く,自分のものにできれば多くの場面で役立つはずです。
ここでは学習のしやすさを考慮に入れ,スピーチを内容的に9個の段落に分けました↓
段落ごとのスピーチ内容
第1段落:祝辞(1分25秒~)
第2段落:ピアノ演奏と東日本大震災(2分14秒~)
第3段落:被災地の様子(4分23秒~)
第4段落:第1次安倍政権の崩壊から総裁復帰までの心境(6分49秒~)
第5段落:決して諦めないことの重要性(8分36秒~)
第6段落:失敗と挑戦(10分32秒~)
第7段落:コロナ禍がもたらした絆(11分34秒~)
第8段落:世界に誇れる日本人の姿(12分38秒~)
第9段落:結びの言葉(14分10秒~)
次章以降では,上述した3つの段落を1つのかたまりとして捉え,TOEICで重要となる表現や文法事項を英語音声や原稿と共にそれぞれみていきたいと思います。
安倍元総理の英語スピーチ前編に出てくる重要表現

まずは前編ですが,英語音声はこちらです↓
第1段落
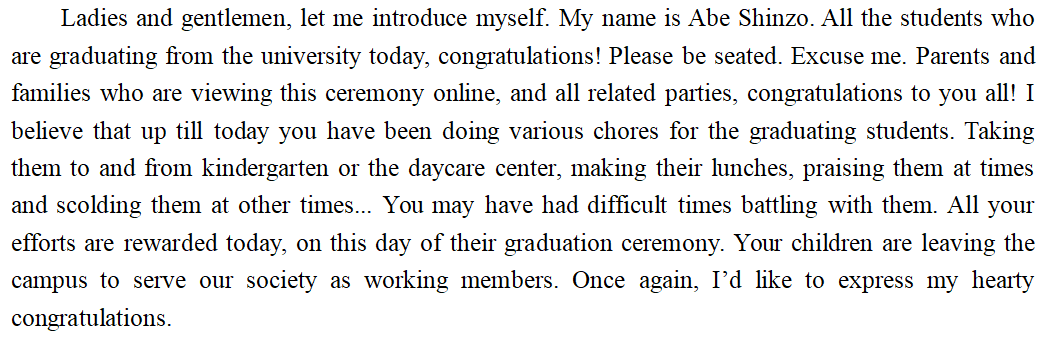
スピーチは祝辞を述べるところから始まりますが,その内容はどちらかといえば大学生の周りにいる保護者に向けられたものであり,1人の人間を自立させるに至ったことに対する労いのように聞こえます。
早速出てきたletですが,使役の動詞ということでintroduceが原形になっているところに注目しましょう。
Let'sという単語はみなさんご存じでしょうが,その元の形はLet usだったりします。
All the students who are graduating from the universityという文ですが,関係代名詞のwhoでstudentsが修飾されているのでtheが付いているわけです。
その他,All the~という言い方にも慣れておきましょう。
この段落では全体的に現在進行形が多く使われていますが,今まさにそのための準備をしているのであれば,確定度が高い未来のことを示すことも可能です(例:I am visiting Hiroshima next Sunday.)。
単語の中ではpartyという多義語に注目してみますが,「パーティー,グループ,団体,政党,関係者」などの多くの意味があり,ここでは一番最後の意味が近いでしょう。
さて,upを使った「~まで」という表現としてはup toが有名ですが,up till (until) todayと書くと「今日まで」という意味になります。
up toやup untilで,まとめて1つの前置詞のように捉えてください。
なお,普通「デイケア」と聞けばお年寄りのための施設が真っ先に浮かぶものですが,adult day-care centerの意味以外に,今回のようなday-care center for children(保育所)の意味もあります。
文の構造としてTakingからscolding them at other timesのところは完全な文の形をしていませんが,それは前文のdoing various choresの内容を説明したものだからです。
ついでにat timesとat other timesの対比にも注目しておきましょう。
第2段落
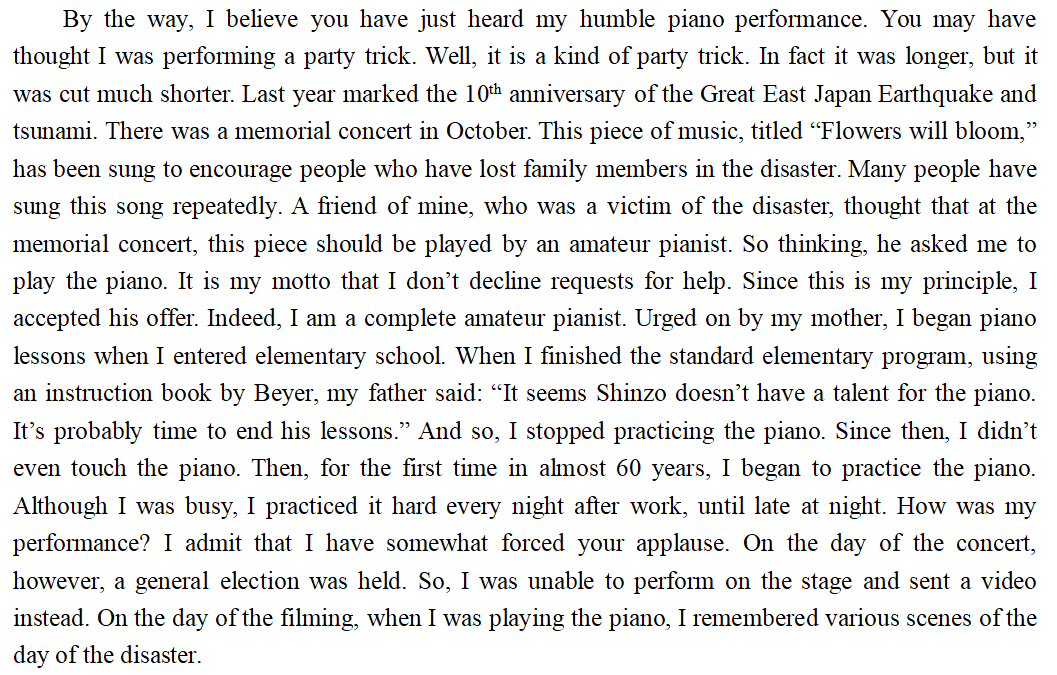
第2段落ではピアノの話が出てきます。
動画の冒頭部分でも安倍晋三氏がピアノを弾くシーンが流れていましたが,ロングバージョンの動画は後で紹介しているので是非観てみてください。
私は「ずいぶん上手い演奏だなぁ」と感心したのですが,披露したのは約60年ぶりと言われていたことに驚きを隠せません。
第2段落のスピーチでは,リーダーとなる者にふさわしい信条めいたものを見て取ることができますが,私が出席した東京大学の入学式でも当時の学長が同じことを言っていました。
なのでこれは安倍氏だけの特殊な考えではなく,リーダー界における共通認識と言うことで間違いなさそうです。
ピアノ動画の長さについて言及している文においてcutという単語が確認できますが,これは過去分詞で「切られる」の意味で受け身になっています。
比較級の強調にmuchを使うことと併せて確認しておきましょう。
Last year marked the 10th anniversaryという英文は,「昨年(2021年)は10周年を特徴づけた」と直訳することができます。
It is my mottoのitはthat以下を指し「頼みを断らないのが私の座右の銘です」という訳になり,Since this is my principle(ご存じの取り,これが私の行動原則ですので)にうまくつながっていくわけですが,これが先に述べたリーダーたるものの資質です。
頼みごとをするとき,相手は「この人だからこそ任せられる」と思っているからこそそのような行動に出たわけで,「頼み事は忙しい人にこそせよ」と並び,相手が有能であるかを判断する際の試練としても使われています。
ここのSinceは,後に出てくるSince thenのそれ(こちらは接続詞ではなく前置詞)と品詞が異なる点に注意しましょう。
なお,Urged on by motherのところですが,my mother urged on me to begin piano lessonsという文が受け身になり,I was urged on by my mother (to begin~)となる関係上,onは必要です。
2つの前置詞が並ぶと不自然に思う気持ちを押さえて,正しい英語を書けるようになってください。
個人的にはfilmという動詞に注目で,「撮影する」という意味としてTOEICにも出てきます。
第3段落

第3段落は東日本大震災の被災地と人の様子について語られますが,同じ大学出身の尊敬できる先輩がいることは誇らしいですね。
なお,オリジナル版の動画で「安倍さんの頑張りを」と間違えて字幕が付けられていたことに気が付いた方は,しっかりと内容を理解しながら聴けていると思います(正しくは「安倍さんも頑張れよ」です)。
amidとはあまり見慣れない前置詞でしょうが,iのところにアクセントがあります。
綴りをよくみるとmidという英語が隠れているのですが,「~のまん中に;~のさなかに」と訳してください。
その他,discussやreachは他動詞なので直接目的語(the matterやanother town)を取っている点,the day when(~という時)やMr. Suma Tokuhiro, the president of a shipping companyに見られる同格表現に加え,while (they were) holding back their tearsのように主語+be動詞の省略があることに注意しましょう。
なお,I shallやwe willのところですが,I'llやWe'llなどと短縮形にしていないところに話し手の強い意志を感じ取ることができます。
安倍元総理の英語スピーチ中編に出てくる重要表現
続けて,英語スピーチの中編にあたる第4段落から第6段落までを見ていきましょう。
音声は以下で確認してください↓
第4段落

第4段落ですが,話題が第1次安倍政権の閉幕や安倍さん自身の持病といった,困難な時期を過ごしたことに移ってきました。
それでも責任は自分にこそあると,他人のせいにしていないところは立派ですが,再度立ち上がるための自信はどうしても持てなかったようです。
それは新薬が開発され持病の問題がクリアされても改善されなかったようですが,被災地で強く生きる人の姿を見たときについに決意が固まります。
「就任」という意味の単語としてはinstallationやinstallmentがTOEICに出てくることが多いように思いますが(後者は「分割払い」の意味も重要),inaugurationも同レベルの単語とされます。
run for~という熟語は知りませんでしたが,調べると「~に立候補する」という意味があるようです。
この段落ではcrushing defeat(惨敗)やdeadlock(行き詰まり)を筆頭にネガティブな単語が数多く見受けられるのですが,最後の方ではreviveやrestore,regainといったポジティブな意味の単語が目立ち始めます。
J-POPで言うところのBメロの最後の部分ではないですが,第5段落というサビに向かってテンションが高まってきた感じがありました。
第5段落

今回のスピーチの中で,私は第5段落で語られる内容が一番好きです。
単純なことかもしれませんが,真理というものは大体わかりやすい形をしているもので,自分探しに出かけた人が結局自分自身の中にそれを見出す話はよく聞きます。
「決して諦めないこと」と「自分に自信を持つこと」。
この2つは教訓としてしっかり自分の中に刻んでおきたいものです。
英文についてみていきますが,Becauseで始まる英文を書くのは特別な場合を除いてできるだけ避けたいもので,今回の翻訳のように,その前にIt isやThis isを付けることで問題なく使うことができます。
step forwardという語句がつんくさんの曲の歌詞の中と安倍政権を一緒に支える素晴らしい仲間について形容する際とで共通して使われているあたり,English versionの文章もよく考えられているように感じました。
なお,TOEICの単語帳で学んでいるとstep down(辞任する)は頻繁に目にします。
また,I promised to never drink alcohol againの英文に見られるように,to neverという語順はいたって自然なものです。
第6段落

今回のスピーチでnever give upと並んでキーワードになる表現はrise up(立ち上がる)でしょう。
少年向けのマンガで目にすることの多い教訓の筆頭ですが,大切なことというのは何回も繰り返して説明するくらいがちょうど良いと感じます。
健康であって普通に1日が送れることのありがたさは,自分が病気やけがの状態になってみない限りは忘れがちです。
You may fail, but rise up again!のような英文の形で覚えて,すぐにでも使える状態にしておきましょう。
第6段落のスピーチの目的は失敗しても挑戦することの重要さを伝えることですが,ここではDisneyの創設者の話が例として登場します。
私が聞いたことがあるのは「紙吹雪にあえて丸い形のものを使った」という話で,「地面に落ちたときに隠れミッキーのように見えるから」と社員に説明したそうですが,ウォルトディズニーという人物に関しては実にたくさんの魅力的なエピソードが知られています。
TOEICに出る単語としてはtake on(引き受ける)が大切です。
安倍元総理の英語スピーチ後編に出てくる重要表現
英語スピーチの後編は第7段落から第9段落を扱います↓
第7段落

第6段落からすでに話題の中心は卒業生に移っていましたが,第7段落ではコロナ禍で困難な状況を経験したこととそこでしか築けない絆についての話が展開されます。
これが,第4~5段落で述べられた困難や素晴らしい同僚の話と重なってくるわけです。
英文の解説をしますと,先ほど紹介したThis is becauseに対する表現がThis is whyであり,1語で表すとSoに近い意味合いとなります。
not~very(あまり~でない)という表現の他,not A or B(AでもBでもない)やonly a few(ほんのわずかな)といった否定語があったり,同じ「困難」という意味を表すにあたってrestrictionsやhardshipsにdifficultiesといった複数の単語を使い,同じ単語ばかりを繰り返さないための工夫だったりを学びましょう。
ちなみに,スピーチに出てくるyouという単語の多くは「あなたがた」と複数の意味で使われています。
とはいえ,自分1人に向かって話しかけられている感じがするのは,youが「あなた」という単数の意味でも使われるからでしょうか。
fosterは育むという意味で「友情」以外に「子どもを育てる」という意味でもよく使われます。
第8段落

第8段落では,卒業生の自信に繋がるエピソードが語られますが,ここでの日本人の姿はまさに美しい国に生きる人に他なりません。
多くの単語が出てくるのでしっかり学んでおきましょう!
具体的にはengulf(飲み込む)やcalamity(災難),decently(礼儀正しく)やwield(巧みに使う),shout oneself hoarse(声が枯れるほど叫ぶ)といった語句の他,TOEICに頻出なのがevacuation(避難),rubbleやdebris(両者とも意味は「がれき」)です。
ちなみにdeprive A of Bは「AからBを奪う」という意味ですが,英語圏の人の発想は「BからAを奪う」となっていて,このofはoffに似た意味があります。
ゆえに上のスピーチの場合,「normalでpeacefulな日常生活から多くの人を奪い去った」というのが英国人の見方となり,rid A of Bやrelieve A of Bのときも同じ考え方です。
第9段落

これまでの第6~8段落を聞いて,困難を共にした仲間の存在に気づき,自分に自信を持てるようになり,失敗を恐れずに挑戦できるようになったように思いますが,第9段落でも再度念が押されて結びの言葉となっています。
これまでに語った内容を振り返るとともに,使われている表現もどこかで目にした単語が多いですね。
英文の内容的には2つ目にある文がやや意味を取りづらいですが,「熱意ある彼らが,私に若者に対する大きな期待を受け入れさせる」と直訳することができます。
なお,My young friendsというのは呼びかけで,ここでのurgeはurge 人 to do(人に~するよう勧める)という形で使われていることが注意点です。
さいごに
2022年7月8日に安倍晋三氏の訃報が流れ,私はその後になってようやく本スピーチの存在を知ることができました。
最初は何となくの気持ちで視聴してみたのですが,話の構成はもちろん,間の取り方であったり表情や抑揚の付け方だったりは流石の一言で,若者に贈るスピーチとして全世界に誇ることができるものと確信したことが当記事を書くに至ったきっかけです。
このスピーチは,これからの未来に生きる若者だけでなくあらゆる人々を前向きな気持ちにしてくれるものであることに異論の余地はないでしょう。
上で見てきた原稿はあくまでEnglish versionのものであり,安部氏本人がスピーチした日本語とは当然ながら異なりますが,元が素晴らしい内容であるため,翻訳されたものであっても何らその輝きを失っていません。
是非何度も動画を観ながら英文を読み直し,時には暗唱したり日本語のスピーチに合わせて英語を話したりしてみてください。
最初は全然オリジナル版のスピーチの魅力が伝わるような読み方はできないでしょうが,安倍さんだったらどのように読み上げるのかを考え,そして動画を観ながら実際に英語を話してみることが大切です。
そして数をこなしていくと,少しずつではあるものの自分の発する言葉に力強さのようなものが宿ってくることに気が付くことになるでしょう。
最後になりましたが,安倍晋三という偉大な人物と同じ時代を生きられたことを感謝し,今回のスピーチを通して得られた沢山の教訓を私自身これからの人生に役立てていくことをここに誓います。
どうぞ安らかにお眠りください。