何もTOEICに限らないのですが,どんな英語学習においても真っ先に行うべきは「単語学習」です。
英文を読むときや空欄に単語を入れる問題の役に立つことはもちろん,リスニング問題で間違えた原因について考えてみても,その多くは聴いた音と単語が結びついていないせいでしょう。
英語を話す場合においてすら,語彙力が不足しているがために満足に話せないことが少なくありません。
例えば,赤ちゃんの「よだれかけ」は英語でbibと言いますが,もしこの単語を知らなければ
a piece of cloth or plastic tied under a baby's chin to protect its clothes when it is eating
といった具合に長々と説明する羽目になります。
わずか1語で済むはずのところをこのような英文で言うのは煩わしいですし,説明のところで使用している「tie」や「chin」といった単語が頭に浮かんでこなければ完全にお手上げでしょう。
もちろん,bibは難しい単語ですしTOEICにも出題されないでしょうが,逆にTOEIC頻出のものについては初心者には難しいとされる単語であっても覚えるようにすべきで,このことこそが「TOEICの単語は専用の教材を使って学ぶべき」だとされるゆえんです。
今回の記事で「単語の勉強法」の3つのポイントについてみていきましょう!
もくじ
基礎単語を覚える
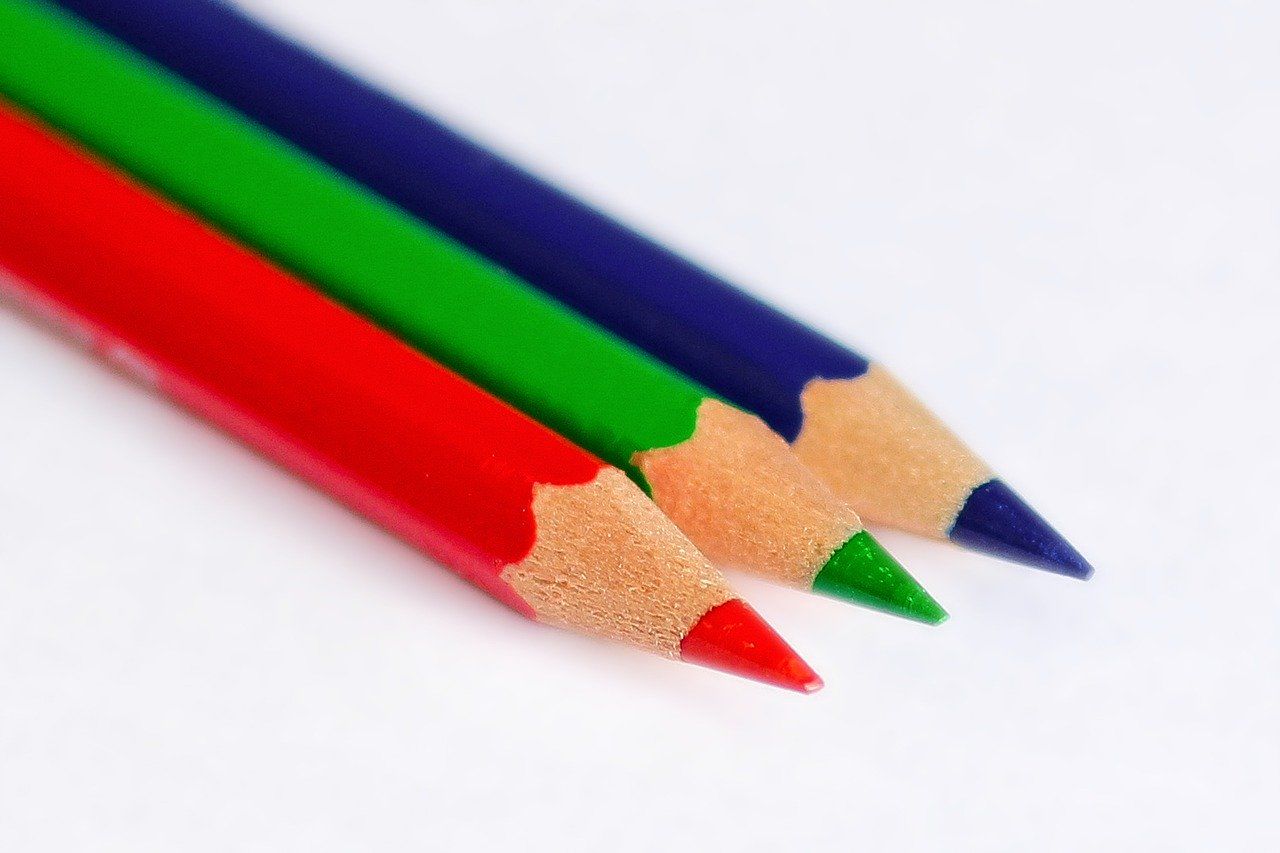
TOEICスコアが200~300点レベルの方であれば,中学校までに習う約900語の発音と意味とが頭の中で一致していないはずで,TOEICのリスニングでは内容をほとんど理解できないはずです。
「battery(電池)」とか「virus(ウイルス)」などの単語は特に聞き慣れない発音になるため,TOEICの中級者であっても音を聞いただけでピンと来ることは少ないでしょう。
私自身,最初にこれらを耳にしたときは非常にびっくりしたことを覚えています。
ところで,みなさんは
中学英語だけで英会話ができるようになる
という話についてご存じでしょうか。
これは決して大げさに言っているわけではありません。
実際,80年くらい昔にCharles Kay Ogdenというイギリスの言語学者が開発した「Basic English」なるものが知られていて,日常で使う英語表現はわずか850語の英単語ですべて言い換えられてしまうことが知られています。
音は聞けませんが,アルファベットだけみて意味がわかる単語が大半であれば問題ありません↓
ちなみに,英語を自由に操るネイティブであれば日常会話に2~3万語を使うと言われており,それと比べれば20分の1以下の数ではあるものの,わずか850語であっても完璧に使いこなせるようになれば,英語を話すときの不安が大きく減ることは確かです。
これらは基本単語ですから,わからない単語が出てきたときもこれら基本単語のどれかと似た意味であることがほとんどであるため,それについて知っているだけでもかなりの安心感に繋がります。
なので,まずは中学校で習う単語の勉強から始めるようにしてください。

そのときの教材としては,日本語訳や単語の説明があって文章の意味内容がわかりやすいものを選ぶのがポイントで,音声をしっかり聴けるものを選びましょう。
中学校の教科書があればそれを使うで構いませんが,個人的には英語の絵本や童話もおすすめです。
単語は文脈やイメージで覚える

単語ですが,文の中(文脈)で覚えることが一番です。
文を読んでいきながらわからない単語が出てきた際,周りにある単語で意味が分かるものを頼りに,未知の単語の意味を推測するようにします。
ただし,書いてある英語の半数以上がわからないものは教材として不適です。
7~8割の単語の意味がわかるものを教材に選ぶようにしてください。

この方法で学ぶメリットは,単語とその意味をただ丸暗記するわけではない(有意味学習になる)ので,より記憶に残りやすくなるところです。
カラフルなイラストがあったり,すでに内容について知っているものを教材に選んだりすると,場面を想像しやすくなる効果があります。
極端な例ですが,「anemic」という単語(英検1級レベルです)を学ぶ過程で,
My brother is anemic(私の兄は貧血です)
という文で覚えたとしましょう(ここでは「兄」と「アニーミック」の発音を掛けてみました)。
単語を見て,貧血で元気がない兄の様子がイメージとして浮かぶ状態にまで至れば,
We have an anemic rate of economic growth
という英文の意味もなんとなくわかるのではないでしょうか。
正解は「経済成長率が芳しくない」です。
もっとも,このように頑張って覚えた単語であっても,時間が経つと意味を忘れてしまうことになります。
そこで,同じ文章を再度読むようにすれば,初回の時より思い出すためのきっかけが増えていることにすぐ気づくでしょう。
この単語の意味はなんだっけ?
周りでこういう意味の単語が使われているから……あ,確かこういう意味じゃなかったか
などと記憶の扉を何度もノックすることができると,結果としてその単語が記憶によく定着します(専門用語だと「retrieval:検索」と呼ばれます)。
「この単語,どこかで見たことがあるけど,どんな意味だったっけ」と思ったら,その都度調べるようにしましょう。
TOEIC用の単語帳を利用する

冒頭部分でも触れましたが,単語帳を使う場合はTOEICテストの頻出語句を意識して作られた専用のものを使うようにしてください。
1つの単語につき1つの意味が書かれている単語帳は,前章の内容からすれば記憶に残りにくくなりそうですが,一定時間で多くの単語に触れられる点は魅力的です。
ところで,教材によっては,単語と意味以外に派生語や類義語までが掲載されているものも少なくありません。
具体的には以下のような感じになります↓
- 類義語=condemn,force,impose,oblige,obtrude,urge
- 派生語=success,succeed,successive,successful,succesor
TOEICの初心者は「類義語」を見ると混乱してしまう傾向にあるので無視するか,可能であれば「派生語」のみが載っている教材を選んで使うようにしてください(とはいえ,多くの単語帳は両者が掲載されているでしょうから,類義語は無視して覚えていく方針で進めて構いません)。
また,文を読んでいて知らない単語に出会ったときには辞書を引き,その意味をその都度ノートに書き写すことでオリジナルの単語帳を作ることができます。
数にして全部で数千語を書くようなことにはならず,先述したように初心者はせいぜい1000語弱を覚えれば良いとされているわけですから,覚悟を決めて頑張りましょう!
少数精鋭になる分,辞書の最初の意味や定義だけを写して終わりとはせず,書かれている全部の説明に目を通して,書き留められるところをなるべくたくさん写し取ろうとする姿勢が大切です。
例えば,TOEICに頻出の「curb」という単語をノートに残す場合,
- curb /kə:b/
- 名「歩道の縁石」「抑制」
- 動「抑える」curb ~'s cries(泣き声を抑える)
などとまとめることになります。
このときに,もし同じ単語を再び間違えてしまったらどうすれば良いでしょうか。
その場合は,前回のことは気にせずにもう一回書き写せばOKです。

まとめ

以上,TOEIC初心者が実践できる単語の勉強法を紹介してきました。
英単語の意味を言えるようにする以外にも,日本語を見て英単語を答えてみたり,単語をノートに声に出しながら書き写したり単語帳にしてみたりなど,覚え方には色々な工夫が考えられるはずです。
単語帳自体も,単語が頻出順に並んでいるものの他,リズムに乗って学べるものだったり,アプリ学習できるものだったりと,独自色の強いものがよく売れています。
当記事の最下段にある「単語」のタグをクリックすることで,様々な単語帳のレビュー記事を読むことができるので参照してみてください。
また,ノートという形態にこだわらなくても,「Quizlet」というスマホを使えば単語帳を自作することが可能です↓
なお,世の中に出ている勉強法は,本人が自由にアレンジした方法であることがほとんどで,誰かがそれで上手くいったからといってそれが自分に合うかどうかは実際にやってみないとわかりません。
とはいえ,今回紹介してきた方法は比較的多くの人にうまくいくことがわかっているものなので,まずはその通りに実践し,学んでいる中で自分がやりやすいと感じるやり方が見つかったら,そちらを取り入れるようにしてほしいと思います。
自分にとって適した方法というのは,とにかく続けやすいものです。
それを判断基準にしてください。
今回紹介した方法で単語力を高めたら,次は文法力を高めて,あとはリスニングについて学んで中学英語を完成させましょう。
そうすれば初心者レベルを卒業できます。
その後の学習も含めて,是非,目標スコア別のTOEIC勉強法についての記事を読んでみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。