今回は「TOEICの歴史」についてまとめてみることにしました。
というのも,私がこれまでに知っていたことは,L&Rテストの形式がこれまでに数回変わったことや,TOEIC Bridgeのような新しい試験が過去に追加されたことくらいで,例えば,一体どのような目的で生まれることになったかは,この記事を書くまで知りませんでした。
TOEIC対策として様々な教材に触れてきましたが,たとえ公式問題集であってもその歴史についてまでは記載されていないわけで,意外と多くの方が知らないのかもしれません。
歴史について知ったからといってスコアアップすることには繋がりませんが,より親しみをもって対策できるようになる可能性があります。
記事を読むのにそれほど時間はかからないので,是非,学んでいってください!
もくじ
TOEICの生みの親は日本人だった

TOEICの誕生について語るためには,なんと1970年代にまで遡る必要があります。
その頃の日本といえば,第4次中東戦争に端を発した石油危機が起こって経済的に打撃を受け,日本の輸出超過が原因となり,アメリカなどとの間で貿易摩擦が問題になっていました。
いわゆる,高度経済成長の影の部分になりますが,翌年の1974年には経済成長率(実質GDPの対前年度増減率)がマイナスに転落しています。

ちょうどその頃,先進国はそれまでの固定相場制から変動相場制への切り替えを開始し,1976年にIMF暫定委員会で承認されました。
そのような時代だったので,日本は海外に進出してコストカットや効率化を図りつつ,先の貿易摩擦の緩和を目指すことにしたわけです。
そうなると,世界中の人と互いに理解を深めていくために,英語でのコミュニケーションが必須となります。
つまり,知識としての英語よりも道具としての英語運用能力が求められるようになったわけですが,当時の状況はあまり良くありませんでした。
英語力不足が原因で,国際的な商談や会議の場では実力を発揮できず,苦労しているビジネスパーソンは多かったわけです。
そんな中,アメリカのニュース雑誌を発行するTime社に24年間勤務していた北岡靖男氏(1928~1997)と,通商産業省(今の経済産業省)で国際的な経験を積んだ渡辺弥栄司氏(1917~2011)の2人が運命の出会いを果たします。
1974年に北岡氏が国際コミュニケーションズを設立したわけですが,渡辺氏の所属する日中経済協会のオフィスが同じ青山ビル内にあったわけです。
彼らは英語教育について話し合い,
英語教育発展のために,何か実効性のあるプログラムを開発しよう!
という着想でもってTOEICを開発することになります。
TOEICテストはいつ誕生したか
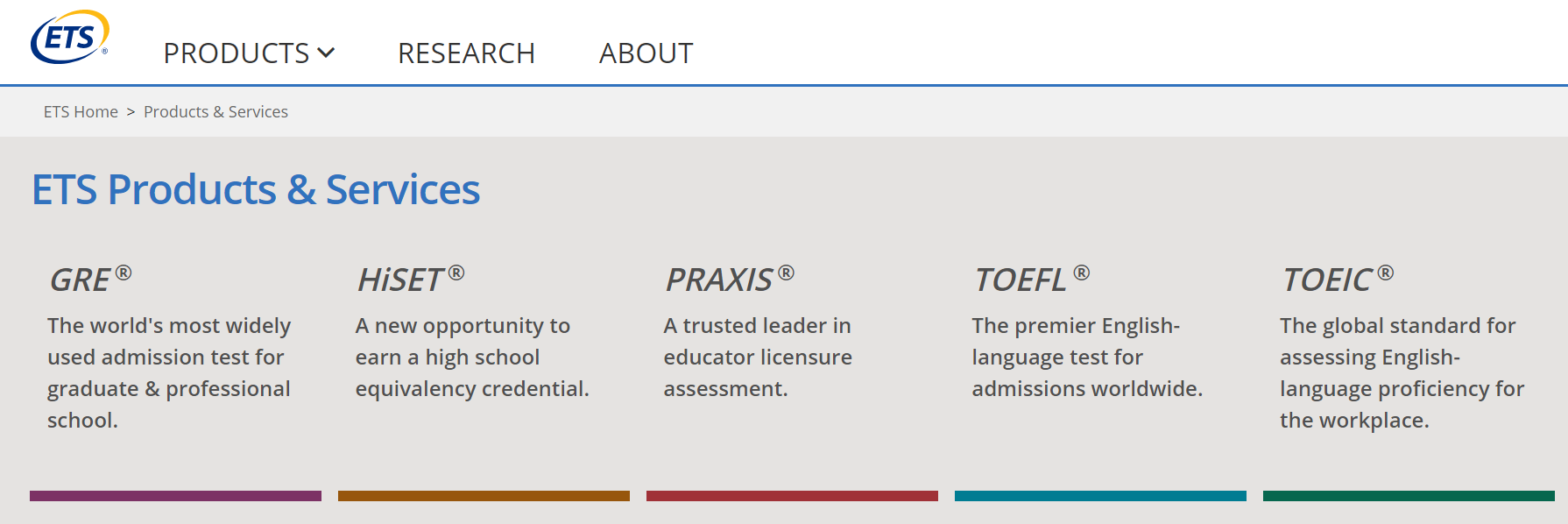
当時,世界最大の非営利テスト開発機関だったのは,アメリカのニュージャージー州にある「ETS」です(設立は1947年です)。
この機関に先の2人が目をつけるようになったきっかけは,国際コミュニケーションズの同僚だった三枝幸夫氏(1931~2005)の助言があったからだと言われています。
TOEFLやSAT(全米大学入学共通試験)もETSが作っていたわけですが,ここが製作するテストの特徴は,
- 信頼性:何度受けても同じ基準で評価される
- 妥当性:受験生の特徴や特性,知識やスキルを定義通り測定できる
- 公平性:言語や問題内容で受験者の有利・不利が生じない
という3つの開発理念によく表れています。
独自の調査研究に基づき,統計分析の専門家のチェックが毎回入ることになるので,受験生が同じ実力のまま何度テストを受けようとも,大きくスコアが変わることはありません。
そんなETSと先の日本の発案者たちが交渉を開始したのは1977年の9月のことです。
当初は,遠く離れた日本から来た訪問客の,それも個人の依頼だということで難色を示したETSでしたが,粘り強い交渉が実を結び,その後2年間の時を経てついにTOEICテストが誕生することになります。
まとめると,2人の日本人がアイディアを持ち掛け,ETSがTOEICを開発することに成功したというわけです。
国内においては,渡辺氏がテストの実施・運営組織作りに動いており,通商産業省の認可を得たTOEIC運営委員会が設置され,記念すべき第1回が1979年の12月に札幌・東京・名古屋・大阪・福岡の5ヶ所で実施されました。
以下に,これまでのTOEIC関連のテストが誕生した経緯を表にまとめておきます↓
| 年代 | できごと |
| 1979 | TOEIC L&Rテスト第1回 |
| 1981 | 団体特別受験制度開始 |
| 2001 | TOEIC Bridge L&R開始 |
| 2006 | TOEIC L&Rがリデザイン |
| 2007 | TOEIC S&W開始 |
| 2016 | TOEIC L&Rがアップデート |
| 2019 | TOEIC Bridgeがリデザイン |
| 2025 | テスト結果のTOEICロゴを刷新 |
なお,現在TOEICの運営をしている国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)が設立されたのは1986年になってからで,現行のTOEIC L&Rテストは2016年の変更を経た新形式です↓
2025年の4月から新しいロゴが採用され(教材は24年7月から),カラーが青から緑になりました↓

アスタリスクと上向きの斜線が入ったシンボルは「The Source」と呼ばれ,教育及び人材ソリューションにおいて,ETSが従来の測定基準や業界標準を再定義して,より効果的かつ革新的なアプローチを確立することを目指すことを表しています。
TOEICと企業の関係について

初回のTOEICテストの受験者は約3千人しかいませんでしたが,1985年度には9万人弱,1990年度に33万人超に達し,2000年度には大台の100万人を突破,そして2019年度には年間で約220万人が受けるほどのテストにまで成長しました(最近はやや減少し,2023年度は176.3万人です)。
この上昇には,企業のグローバル化が進んだことが要因の1つとされています。
少し前であれば,一部の有能な人を選んで行っていた英語研修ですが,1980年後半以降は多くの社員がその対象となり,企業全体の英語力アップを目指す流れが定着しました。
そんなとき,客観的に英語力を評価でき,具体的な数値で目標を達成できたかどうかが簡単にわかるテストが出てきたら,皆が飛びつくのも無理はありません。
英語力のモノサシが不在だった時代において,TOEICの誕生はタイミング的にドンピシャだったというわけです。
そういった理由で,1990年代になると就職時の採用基準として使われ始め,2000年代には昇進や昇格の要件にもなっていきました。
今では大手のグローバル企業以外の,例えば旅館や警備会社やタクシー会社においても研修が行われているほどです。
目標スコアは,いわゆる「おもてなし英語」の習得がメインの場合,500~600点に設定されます。
一度で聴き取れなくても,何度かやり取りしているうちに相手の言いたいことが理解できればよいわけです。
そのようなニーズの拡大に合わせて,初・中級者向けのTOEIC Bridge Testsが開発され,ビジネス現場で話したり書いたりする能力を測れるS&W Testsも登場してきました。
2019年にBridgeが英語4技能に対応したのは,2020年度の入試改革を見据えて,中高生の実力を測る目的が大きかったように思いますが,いずれにしても益々の広がりを見せているTOEICテストです。
日本で発案され,ETSが形にしたTOEICはIIBCによって現在運営されていますが,運営機関は東南アジアやヨーロッパや中南米のような非英語圏にも設置されていて,160ヶ国14000の企業・団体が受験するグローバル・スタンダードな存在になっています。
まとめ

以上,TOEIC誕生の歴史と,企業におけるTOEICテストの変遷についてまとめてきました。
なお,今回まとめた内容についてより詳しく知りたい方は,以下の記事をお読みください↓
冒頭でも述べたように,歴史について知ったからといってTOEICのスコアが上がるわけではありませんが,日本人が発案したテストが今では世界の国々に必要とされていることを知って,TOEICの印象が良くなったことは確かです。
グローバル化の流れは,最近の社会情勢をみても変わっていませんから,これからもTOEICは貴重なモノサシとして世界中で用いられ続けることでしょう。
実際,当サイトの訪問者には日本以外の国からのアクセスも多いです。
社会で活躍したい方は,それ相応の高いTOEICスコアを目指して是非頑張ってください!
最後までお読みいただいた方に感謝して,終わりの言葉に代えさせていただきます。
ありがとうございました。